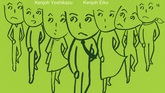第25回社会保障審議会年金部会(2025年6月30日)
○権丈委員 いろいろとお疲れさまでした。この間、結構楽しませてもらいました。
本日の議題に関する全体的な意見に関しては、小野委員、是枝委員と、基本ではなくて全体的に全く同じです。小野委員の働き方に中立的な制度の実現、雇い方に中立的な恒久的な仕組みの構築、そして是枝委員の意見は、参考人として参議院のほうに出席されたときの発言があります。これは、ぜひ皆さん参考にされるといいと思います。特に、本日の資料1の2頁、赤字で書かれた衆議院による修正部分をどう解釈していくかというのは同じであります。
さて、法律が成立した後に言うのも何ですけれども、少なくとも次の2つは年金部会で議論してもらいたかったかなというのがあります。
1つは、厚生年金のマクロ経済スライドは止めるべきか否か。もう一つは、基礎年金の底上げに資する手段として、適用拡大、45年化、国民年金と厚生年金の一元化という少なくとも3つがあるわけですが、いずれを採るべきか、これは、やはり年金部会で議論してほしかったというのはあります。
先週は、生活保護をめぐり違憲判決が出ていました。その際、専門家の知見が十分に踏まえられていなかった点が指摘されていました。そう考えると、今回の年金改正は大丈夫かなというのはあります。
この間の報道では、調整期間の不一致はマクロ経済スライドが効かなかったためとの説明がなされていたのですが、実際には名目下限つきの、言わば偽マクロ経済スライドで運用されていたことが原因だったんですね。それをよしとする人たちは、この年金部会の事務局にも、委員にも、そして傍聴席にもいないはずです。ただ、この偽マクロ経済スライドを容認する人たちは、中小企業に一定の負担を求める適用拡大とか、自営業者や農業者に長期加入を求める45年化という王道の改革を進んで担うインセンティブはほとんどありません。むしろ反対する誘因のほうが強いかなと。
私は、これまで20年近く適用拡大は絶対正義であると言ってきました。しかし毎回様々な形で妨げられてきました。今回もまた、あんこのないあんパンなどの話を含め、議論が本質から逸れていく様子を眺めていたのですが、将来の低年金対策に真摯に向き合うのであれば、適用拡大と45年化こそが有効な手段であって、それ以外の方向へ議論を誘導する人たちの姿は、どうしても私には、いつも邪魔ばかりするばいきんまんと重なって見えてしまうわけです。
適用拡大、45年化こそが大切と考えている人は、年金で汗をかいてもらう方法しか口にしません。政治、政策というのが、易きに流れるのが見えているから、ほかの抜け道はつくらないという姿勢でいます。
ここ数年、国民年金と厚生年金の財政調整方法について、積立金割の導入が議論されていました。これは実質的な制度の一元化なのですが、私は覆面テーマと呼んでいまして、正体が見えないようなテーマで議論されていた。
厚生年金というのは、賃金比例、労使折半の仕組みで再分配機能を備えています。一方、国民年金は所得捕捉の困難な層を対象としているため、定額拠出、定額給付により公平性を保っている。両者は全く異なる設計思想を持っている。小野委員も先ほどその設計思想という言葉を使っていましたが、これらを一元化しようとすると、公平性の問題が多面的に生じてきます。
それらの公平性の問題を回避するために、国民年金で基礎年金の給付水準を先決する方式が考案されたのであって、それを変えるために両制度を一元化しますという話には、普通ならないですね。
皆保険、皆年金政策を展開している日本で、異なる設計思想を持つ制度の間の財政調整は、加入者割までというのは大原則だったんですね。その根幹に関わる変更は、丁寧かつ公開の上で行うべきだったのではないかと思っています。
それで、制度を一元化すると国庫負担が兆円単位で追加され、みんなの給付は増えるのだから、損得論に持ち込めば、労使は最終的には支持をするだろうと考えられていたのか、長く年金は損得論一辺倒になって、制度への信頼を損なう言葉が蔓延して、以前から言っていますけど、年金世論はぼろぼろになっていった。
しかし、労使は損得の話ではなく、これはルールと制度への信頼の話だとして、積立金割の導入を一貫して反対してきました。そうした労使の見識には、私は敬意を表すべきだと思っています。
先ほど佐保委員も言っていた、2019年12月の第15回年金部会で、使用者もこの段階で遠回しだけど、強い表現で明確に反対しています。
積立金割は、被用者間の一元化だからこそ成り立つ仕組みであって、それを今の国民年金と厚生年金の間に適用するのは、制度の本質から逸脱するというのが、私とか、小野委員とか、是枝委員とかが考えていることではないかと思います。
報道では、「国民年金と厚生年金の財政統合にほかならず、理解を得られない」とされていましたが、その理解の得られなさの1つが流用批判として現れているのだろうし、実は一元化への批判点はほかにも幾つもあります。
2004年の小泉内閣時代から旧民主党とその応援団は、一元化を主張してきましたが、年金制度への理解が十分でなかったことから、年金局とか専門家の批判を受けて、次第にその主張は影を潜めました。
そして、今回同じ役者がそろって、就職氷河期世代の低年金というスローガンを掲げて再登場してきたわけですね。
しかし、昨年の分布推計は将来の年金額は世代に例外なく、改善傾向も見られることを示していて、彼らのスローガン自体が疑わしいものでした。
だけど、議論は旧来のモデル年金に基づいて進められ、分布推計が示した明るい未来の視点は無視されました。
言わば、年金においてもポスト真実政治が影を落としていたと言えます。
2019年のいわゆる2000万円の騒動のとき、基礎年金が3割減るという表現が登場した頃、当時の審議官は、国会で野党議員に3割減るのですねと問われて、算数に弱いのでぱっと割り算できないのですと答えて、審議が一旦中断してSNS上で炎上していました。
年金局としては、不用意な言質を避けようと努力していたと理解しており、私は、その姿勢は評価されるべきだと思います。
他方、公的年金保険の防貧機能を強化して将来の生活保護費の膨張を避けるためにも、労使は45年化には、もう長く理解を示していて、また労働側は適用拡大も長く主張してきました。
ということで、今後は分布推計の成果を踏まえて、モデル年金の限界を乗り越えて、若い人たちが将来は年金があるからと安心して働き、将来の生活に展望が持てると感じられるような、少しは希望を描ける制度、社会を実現していくことが重要だと思いますし、実際そのような将来像のほうが、現実に即した姿でもある。
年金制度は賃金システムの欠陥を補完するサブシステムであって、それを支えているのは、労使の拠出による安定財源です。労使による制度への信頼が支えているからこそ、持続可能な年金制度を我々は次の世代に引き継ぐことができるのだと思います。
注目、アテンションを集めるセンセーショナルな言葉で、人々のルサンチマンや敵意を刺激して分断をあおるほうが、メディアも取り上げるし、政治を動かしやすいという現実はあると思います。しかしそれでもなお、メディアをはじめとする全ての関係者が、それぞれの立場において責任ある判断を行って、アテンション・エコノミーの誘惑に流されることなく、事実を尊重し、社会の連帯を育む姿勢を意識するということが大切なんですね。
そうすることが難しい時代であることは分かっていますけど、そのような姿勢を共有していかなければ、社会の根幹が壊れてしまうなと、そういうことを日々考えていて、今回の件を眺めながら、年金も事実を離れた政治の一例になってしまったなと危惧していたことを伝えておきたいと思います。
以上です。