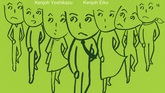第21回会議(2025年6月23日)
○権丈構成員 本日は子育てに直接関係する議題はありませんけれども、先日公表された出生数の報道を受けて、まず一言申し上げたいと思います。こども未来戦略には、「将来に明るい希望を持てる社会をつくらない限り、少子化トレンドの反転はかなわない」とありまして、私はこの文言に深く共感をしています。そして、若い人たちの将来への希望を曇らせている一因というものに年金不安があると考えています。
2週間ほど前に超党派の政策秘書向けの勉強会で、共産、社民を除く全政党の人たちに、「もし将来世代のほうが今よりも低年金者の割合が減って多くの人の年金は増え、将来世代のほうが老後は安泰になるとしたら、日本社会はどうなると思う」という問いを考えてもらいました。消費の増加や出生率の回復、社会全体の安定など前向きな意見が多数出まして、すばらしい国になるとみんな思うわけです。そして、本当はライフスタイルや労働市場の不可逆的な変化もあって、日本の年金の将来というのはそこで話をした明るい方向に向かっていくと見ることもできます。ただ、その勉強会では出席者のほとんど、9割近くですけれども、昨年の財政検証で示された分布推計に初めて触れるという状況でした。
そして、私は彼らにどの政党であれ、年金不信を煽ったりしたら僕たちが立ちはだかるよと話してきました。それは相手は野党であれ、与党であれ、年金局でも同じかなという状況です。
昨年12月に本会議で申し上げたとおり、私は20年近く適用拡大は絶対正義であると言ってきました。ここ数年、政府は勤労者皆保険と呼んでくれていたわけです。これは先ほどの話にもありましたように、道半ばかなと。
そして、今回は国民年金と厚生年金の間の財政調整に積立金割を入れるという話で世の中は盛り上がっていたわけですが、これは大臣もおっしゃっていたように、遠回りしながら落ち着くところに落ち着いたかなという世界です。両制度の財政調整方法に積立金割を入れるということは、古くから言われている一元化と同じ財政効果になります。労使は一貫して反対してきたのですけれども、その理由が世の中に誤解されていてかわいそうだったので、今日は要約して代弁しておきたいと思います。
制度設計原理が異なる国民年金と厚生年金、前者は所得捕捉が難しい人たちがいるから定額拠出、定額給付という制度設計で公平性を担保しており、後者は賃金比例の労使折半の拠出で給付は再分配つきを特徴とする制度です。
この異なる制度間で財政調整を行うに当たっては、医療でもやっており、基礎年金が創設されたとき以来なされてきた加入者割、頭割りが限界で、それを超えて財政調整は明確なルール違反だから反対すると労使はそろって言ってきたのです。
積立金割は被用者年金の一元化のときにも使われていたという説明もありますけれども、それは同一設計原理を持つ被用者同士の制度間だから可能であったわけで、今の国民年金と厚生年金に当てはめるのは適当ではないと多くの人が考えている。
一元化の話は小泉内閣の2004年の頃から旧民主党とその応援団が言っていたわけです。しかし、当時は彼らの制度原理に対する理解不足もあって、年金局や専門家からの反論により実現には至りませんでした。そして現在、あのときの関係者が今回は就職氷河期世代の低年金という新たな理由を掲げて再登場したわけです。
ところが、去年の分布推計で、そもそも就職氷河期という特定の世代の年金給付水準が低くなるわけではなく、先ほども言ったようにライフスタイルや労働市場の変化を反映して、年金額は将来世代ではむしろ増加することがあることが示されていました。しかし、このエビデンスはほとんど知られておらず、年金を見ていると、いわゆるポスト真実政治が年金の議論に影を落としていると見えます。
2019年に2000万円騒動が起こったとき、あの頃の年金局は適用拡大とか45年化を進めていけば、自動的に全員の基礎年金の給付水準も上がるわけだから、所得代替率の低下率で計算した基礎年金3割減をわざわざ言う必要があるのかと考えていたようです。当時の年金担当審議官は国会で野党の議員から3割下がるのですかと言われて、算数に弱いのでぱっと割り算ができないと答えて審議が一旦中断して、SNSで炎上していましたけれども、そのくらい野党やメディアに対して言質を与えないで頑張っていたわけです。
皆保険、皆年金政策を展開する日本で、被用者のための制度とその他の財政調整というのは加入者割までというのが大原則でした。その大原則を変えるという制度の根幹に関わる議論というのは丁寧かつ公開の場で行うべきではないかと思っているけれども、どこでもなされないままに今に至っていると思っています。
この5年ほど、2つを統合すると、追加で国庫負担が毎年兆円単位で入ってくるのだから、損得論になれば労使は最終的には支持するだろうと読まれていたのではないかと思います。しかし、労使は損得の観点ではなく、制度のルールと信頼の観点から積立金割の導入に一貫して反対していました。そして、一方で労使は基礎年金を底上げすることになり、しかも低年金対策としてとても有効な45年化というものは自ら提案していました。労側は底上げに、そして将来の生活保護受給者の削減にも効果的な適用拡大も長く言っている点も尊重すべきだと思います。
政治、政策に関わる皆さんは、この国の年金制度が持つ構造的な強さにもう少し自信を持っていただきたいと思います。私は将来世代の年金が今よりも改善されるという見通しをみんなで共有して、それを信じて政策を進めることが若い人たちの希望にもつながり、ひいては『こども未来戦略』に記されているように少子化トレンドの反転にも資すると考えています。そして、年金局にもかつてのように誤った破綻論を正す役割を担っていただきたいと願っています。政治、行政、労使の各皆さんがそれぞれの立場を尊重しながら、長期的視点で社会保障制度を支えていく姿勢というのが今は求められているのではないかと思っております。
以上です。
フリーディスカッションに入り
○権丈構成員 最初に出生数の報道というところで話したのですけれども、あの話とか、高額療養費とか、その辺の話も関係することになるかもしれないのですが、子ども・子育て支援金というのは、法律上は「実質的な社会保障負担」が増えない範囲内で財源を調達するとあります。どうもメディアとかを見ていると、実質的な社会保障負担というのは何兆円とか幾らという額で論じているような気がするのです。
この実質的な社会保障負担というのは、法律では国民所得に対する社会保険料の比率と定義されておりまして、経済成長に応じた財源確保を行っていくという考え方を定式したものだと思います。実際に新型コロナ以降は実質的な社会保障負担は低下したりして、賃金が上昇すればさらに下がる構造にもなっているということはもう少し思い出していいかなということがあります。
それと、2008年の社会保障の国民会議のときに医療費、あるいは将来の社会保障給付費などの試算とかいろいろやったわけですけれども、その前ぐらいから、名目額で将来を試算すると、足下の経済が成長しているときには将来の給付は物すごく高く推計されて、経済成長率が低くなると医療費や社会保障給付費が低くなるというような傾向があったので、2006年に「医療費の将来見通しに関する検討会」という会議が立ち上げられ、2007年に報告書をまとめています。
報告書では、年金も医療も基本的には経済成長率と、タイムラグはあるけれどもリンクした形で伸びていくから、賃金とかGDPの伸びを先に決めて、そして、その上に近年のスプレッドを上乗せした形で試算していくべきことを確認し、実は、2008年の社会保障国民会議の時からずっと、本当に計算しているのはGDP比だけなのです。
2018年に2040年の試算を行ったとき、そのGDP比をメディアとかに言うと意味が分からないと言われて、試算した彼らはかわいそうに括弧つきで何兆円と書いたのですが、そうすると翌日の新聞は全紙で「2040年度6割増の190兆円」というような報道になる。
本当はGDP比でしか計算していないということを確認すると同時に、先ほど話した支援金関係の「実質的な社会保障負担」というのも同じ考え方にあるということも確認しておいていいかと思っております。