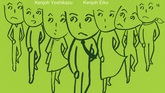次参照
小野正昭さんの発言を紹介しておきます
○小野委員 ありがとうございます。
多くの点で評価させていただいているのですけれども、時間の関係で課題と考える問題を2点だけ申し上げたいと思います。
まず、適用拡大です。今回の中心テーマは、「働き方に中立的な制度」の実現であったと考えています。その点、企業規模要件の撤廃に関して、お隣の日商の小林委員の御主張を受け入れた当初案などを中心に、ずるずると後退したのは、非常に残念だと感じました。
私としては、働き方に中立的な世界を実現するには、雇い方に中立的であることが重要と指摘しましたけれども、恒久的な仕組みの構築を今後に向かっての課題としていただければ幸いです。
次は、調整期間の一致です。先ほども話題になりましたが、まず、資料3の69ページを見ると、「基礎年金は、国民年金加入者と厚生年金加入者が、負担能力に応じて支え合う仕組みです」とありますけれども、「ん?」と思ってしまいました。
これまでは、厚年被保険者の標準報酬に対応する収入が定義できないために、国民年金は定額負担、定額給付とされたと理解していました。つまり、この2つの制度は、もともと設計思想が異なるわけです。また、基礎年金の給付水準の低下問題は、2009年の財政検証から分かっていたわけですけれども、歴代事務局は、調整期間の一致は財政統合であるために慎重だったようです。
しかし、今回事務局は、その方針を転換したと理解しています。いろいろ難しい説明はありましたけれども、私は、調整期間の一致は国民年金と厚生年金の財政及び積立金を統合すれば実現可能だと考えます。なぜなら、スライド調整の終了時期というのは、公的年金全体で財政均衡期間終了時の積立て度合いが1となるように求めるだけで済むからです。
仮に統合してしまえば、基礎年金勘定、基礎年金拠出金等々の、勘定や勘定間の複雑なやり取りは不要になると思います。
これは結果として、調整期間の一致が実現した後に分別管理を維持することの根拠は、積立金按分を用いる厚生年金の実施機関間の負担調整という、厚生年金全体の財政には影響を与えない運営の枠組み、これが根拠になるという非常に際どい状況になるのではないかと思います。
公的年金は、歴史上の経緯を経て緻密に設計されております。したがいまして、私は、コンセプトが異なる制度の安易な統合には反対しますが、本件がそうしたことに通じないか、十分な検討が必要と思っております。
次期財政検証は、議論の整理とか、法律の検討規定及び国会の附帯決議で提示された難しい問題が山積しております。事務局におかれましては、ぜひとも綿密に御検討いただきたいと思います。今度は、一国民として期待しております。
最後に、年金数理人として、今回の財政検証における数理課のすばらしい仕事に敬意を表するとともに、法改後の数理計算結果をお示しいただいたことに感謝を申し上げます。
以上です。
連合の佐保委員の発言もどうぞ。
○佐保委員 ありがとうございます。
昨年末から改正法の成立までの間の厚生労働省事務局をはじめ、皆様の御対応、お疲れさまでございました。
私からは被用者保険の適用拡大と、将来の基礎年金の給付水準の底上げについて発言いたします。
最初に、被用者保険の適用拡大についてですが、企業規模要件の完全撤廃の時期を2035年とされたことや、5人以上の個人事業所の非適用業種への適用を新設、既存という概念で区分した上で、既存事業所は、当面見送りとされたことは、部会の議論の整理から後退した内容と考えており、給付水準の底上げが重要であるからこそ、早期に少なくとも2030年までに適用拡大を進めることに徹するべきだったと考えております。
これに対し、資料に掲載されているとおり、衆・参両院の厚生労働委員会で、早期の任意適用を進める方策を講じていくことを求める附帯決議が採択されております。また、参議院の厚生労働委員会では、国内の外国公館で働く日本採用の多くの人が長年にわたり、被用者保険に加入できていない状況への対応を求める附帯決議も採択されております。
勤労者皆保険を目指している政府として、これらの附帯決議に基づく対応を早期かつ着実に行っていただきたいと考えております。
次に、将来の基礎年金の給付水準の底上げについてですが、改正法に書かれた措置について、経済情勢によって発動する場合、しない場合があると理解しておりますが、発動要否は、財政検証後に年金部会で議論すべきであると考えておりますし、発動する場合の具体的な方法についても、年金部会で議論すべきであると、これは言わずもがなだと思いますが、これらはお願いしたいと思います。
連合としては、給付水準の底上げは極めて重要な課題と認識しておりますが、例えば、基礎年金への拠出ルールに厚生年金積立金を活用することは、従来の拠出ルールの大きな変更であり、底上げに伴い必要となる国庫負担財源確保の方策が明らかになっていないことや、国民の理解も十分とは言えないと考えております。
基礎年金の給付水準の底上げに向けては、国民年金保険料の拠出期間の延長を次期年金制度改革において確実に実施するほか、被用者保険のさらなる適用拡大など、基礎年金拠出ルールの変更以外の他の方策による底上げについても改めて検討すべきと考えております。
なお、5年以上前に厚生年金と国民年金の積立金を統合するという内容の報道がありました。これを受けて2019年12月の第15回年金部会において、積立金統合に対する厚生労働省の見解を当時確認させていただきました。その際には、積立金の統合といったことが先取りとして、答えとしてあるというものでは一切ないこと、積立金の統合というものは、通常は制度統合でもない限りは、議論の俎上にも上がらないようなものであることなどの御見解をいただいております。この見解は、現時点でも変わっていないのかどうか確認をさせてください。
私からは以上です。